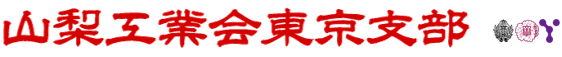山梨大学から海外へ

〜インドネシアでの水力発電所建設を通じて感じたこと〜
■自己紹介
名前:尾田健太郎(おだ けんたろう)
出身:島根県
年齢:33歳(平成3年生まれ)
2010年4月 山梨大学工学部土木環境工学科入学
2014年3月 山梨大学工学部土木環境工学科卒業
2014年4月 清水建設入社
2019年1月~2020年8月 インドネシアで水力発電所建設工事に従事

■海外勤務
赴任先はインドネシア北西のスマトラ島のジャングル地帯。異国で、水力発電所の建設工事に従事しました。ジャングルを切り開き、ベースキャンプの建設や、道路整備などの工事初期に携わらせていただきました。日本のように高度な技術を有する技術者・技能者や高品質な資機材がない中で工事を行う必要があり、思い通りに進まない日々の連続でした。また、文化や慣習の違いにより戸惑いもありましたが、現地の仲間たちに支えられながら、水力発電所を建設するために工事を進めることができました。


■海外生活
海外生活(海外駐在員生活)は自分の時間を確保できることが魅力の一つです。移動はドライバーが、家事・食事はメイドさんが行ってくれるため、移動や家事・食事の準備時間は趣味(YouTube観賞)や自己研鑽などに充てることができました。また、異国の地を旅することができることも魅力であり、定期的に長期休暇を取得することができるため、隣国を観光したことは非常に良い思い出です。食事についても私はローカルフードがおいしいと感じました。ナシゴレン(チャーハン)やミーゴレン(焼きそば)などをほぼ毎日いただいていました。また、鶏肉料理も豊富で、ソトアヤム(鶏肉スープ)が印象に残っています。そのほか、インドネシアはフルーツがとても甘くて、おいしかったです。特にスイカとパイナップルは、日本のものとは比べ物にならないくらい甘かったです。フルーツの王様ドリアンやランプータン、ドラゴンフルーツ、マンゴスチンなど日本ではなかなか食べられないフルーツもあるので、是非一度ご賞味いただきたいです。



■海外文化
海外は宗教が日常生活に深く溶け込んでいます。インドネシアはイスラム教徒が約9割を占めており、一日5回のお祈り時間には多くの人たちがモスク(礼拝堂)へ向かい、お祈りをしています。食事も制限があり、豚肉料理はレストランで提供されないことも多く、文化の違いを肌で感じる毎日でした。また、食べる際は右手で食事をする習慣があり、ご飯やおかずを器用に食べていました。私も何度か挑戦しましたが、なかなかうまく食べることができませんでした。異文化に触れることで、自分の価値観が広がり、視野が広くなったと感じます。
■英語が苦手でも大丈夫
私は英語が得意ではありませんでしたが、運よく海外勤務を経験することができました。今でも英語は苦手で、何度も、聞き返しています笑。ただ、現地では簡単な英単語や筆談、現地語などを駆使してコミュニケーションを取っていました。言葉が通じなくても、伝えようとする姿勢があれば、相手も聞いてくれ、何とか意思疎通することができました。むしろ、伝えたいことが何かを明確にすることの方が重要であると感じました。伝えたいことが明確であれば、何とか伝えることができます。仕事をするうえでは、英語力より技術力の方が重要であると感じています。

■最後に
将来の選択肢の一つに「海外で働く」ことを加えていただけたら、良いなと思っています。私は学生時代、海外で働くことは夢にも思っておりませんでしたが、いざ、海外勤務を経験すると毎日が刺激的で、本当に貴重な経験をすることができました。自分の人生の幅を広げてくれ、自分にとって大きな財産となっています。皆さんにもそんな経験をしていただきたいと思っています。